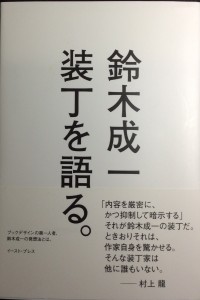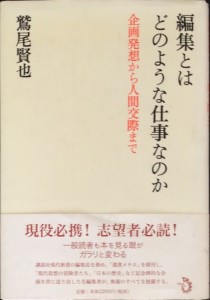『編集者の仕事』(柴田 光滋著、新潮新書、2010年発行)
新書版、208頁、定価700円+税

著者の柴田さんは新潮社で40年間編集経験をもつという方。本書は大学の講座での授業経験から生まれたとのこと、初心者向けにやさしく書かれている。実際に編集に携わる人へのマニュアルではなく、編集の仕事について一般教養レベルでの説明である。
本文は5部からなる。
Ⅰ 本とはモノである
Ⅱ 編集の魂は細部に宿る
Ⅲ 活字は今も生きている
Ⅳ 見える装幀・見えない装幀
Ⅴ 思い出の本から
Ⅰでは、本作りはモノを作る作業であることを、繰り返し説く。
書籍は「心得のある編集者が丁寧に作業した本か、技量のない編集者が適当にやった本かは歴然としている」(p.16)
読みやすく、心地よく頁を繰れる本が良いと言い、具体的な作りの良しあしとして次の点を例に挙げている(pp.15-23)。
・スピン(リボン)がある
・開きが良い、あるいはのど側の余白がある
・目次が内容を伝える
・目次の体裁が良い―書体や行間のバランス
テキスト(原稿)は一次元、本は三次元。本からテキストを抽象的に取り出すのは間違い(p.30)。
モノなので細部までちゃんと仕立てないといけない(p.24)。
書籍の編集はどこかで職人仕事に近い(p.31)。
本は工業生産品ではない(p.31)。
Ⅱは、本文の体裁を中心にしており、技術的な細かい説明もある
個人的には、書籍の編集に関して、微妙なところで用語や仕様が標準化されていないように感じている。本書を見ていくつか新しく理解したこともある。
例えば、四六判は127mm×188mmが標準とされているが、実際の本をモノサシで測ってみると数ミリの相違がある。どうやら製造の誤差だけではないようだ。本書によると、四六判は出版社によってサイズが微妙に異なるということで、柴田さんが長年手掛けてきたのは、130mm×191mmで新潮四六判といい、本文の行数を増やしたい時、ぎりぎりで133mm×191mmも可能(p.43)だそうだ。
実際の本ではいろいろな場所にいろいろな扉が使われている。一方、最近はEPUBの仕様書(英文)にもNaka-Tobiraという用語が登場している[1]。W3Cの文書でもNaka-Tobiraという言葉が、英語で随所に出てきている。おそらく、『日本語組版処理の要件』の影響だろう。
しかし、中扉は特に用語として不統一と感じており気持ちが悪い。つまり、①1冊の本が幾つかに分かれる時に挿入する表題を扉の形式で入れるという説明([2])と、②本文が始まる前に書名を掲げる扉という説明が二つみられる。本書では扉については次のような説明がなされている(pp.57-59)。
・別紙の本扉:書名を記した別紙。別丁扉ともいう。目次の前にある。単行本にある。
・本文紙の本扉:本文紙の最初(1頁目)の扉
・目次扉:目次が2頁以上になる場合は、目次扉を付けるのが一般的。「目次」ないし「書名+目次」を記す。
・中扉:書名を記した扉。目次の後に出てくる。本扉の繰り返しに近い。
・題扉または章扉:章題または短編集の作品名。見出しが独立したもの。
目次扉とか、題扉という用語は、あまり他で見かけたことがなかったのだが、これらは、そのままで意味が通じる・分かりやすい用語なのでもっと普及して欲しいものだ。
[1] EPUB 3.0.1 Changes from EPUB 3.0 2.11 The rendition:align-x-center propertyにThis property was added primarily to handle the problem of Naka-Tobira.とある。
[2] デジタル大辞泉の解説、日本語組版処理の要件(日本語版)もこの解釈。
〇JIS X4051の中扉の定義は「書籍の内容が大きく区分される場合に、その内容の区切りを明らかにするために本文中に挿入する」(91)とある。本文の定義をみると、本文は「書籍を構成する主要部分。通常、その前には前付けがつき、その後ろには後付けがつく」(117)とある。従って、JIS X4051では、本文と前付けの間にはいる扉は、中扉ではないということになるだろう。
〇日本語組版処理の要件(日本語版)は、「中扉は,書籍の内容を大きく区分する場合に用いる.標題のために1ページを用い(改丁とする),裏面は白ページにする.」(4.1.1 見出しの種類)とある。ここはJIS X4051と同じだが、その後ろに「大きく内容を区切る要素がない場合は,前付の直後,つまり本文の先頭に書名を中扉として掲げることもよく行われている.」とあって曖昧にしている。
しかし、実際の本を調べると、書名を記した中扉と部または章扉が両方ある本も見つかる。また、章扉の裏に章の本文を入れている本もある。こうしてみると柴田さんのように中扉は本扉の繰り返しとし、題扉・章扉は部や章の表題(見出し)のスタイルの一種と考える方が良いのではないだろうか。このあたりは、実態と要求仕様のかい離が大きいように感じる。